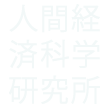研究論文:「国富論」と「道徳感情論」に還る【経済学ルネサンス】<第1回>(全3回)
研究論文:
「国富論」と「道徳感情論」に還る【経済学ルネサンス】<第1回>(全3回)
序文:
<アダムス・スミス以降の経済学暗黒時代>
アダム・スミスの著作が現代社会に与えた影響は極めて大きく、その後の多くの自称「経済学者」や「経済の専門家」がアダム・スミスの後継者を名乗っている。
しかしながら、実のところそれらの自称後継者たちは、アダム・スミスの主張するところを真に理解せず、彼らの都合のよい解釈によって本質を捻じ曲げて世間に流布した。
「すでに終わった理論」であるマルクス経済学はもちろんのこと、近代経済学も意味のない数式を振り回し、ただ人々を煙に巻いただけであった。
マルクス経済学がどれほど役に立たないものであるのかは、マルクスの理論を掲げた共産党に支配された世界中の多くの国々の悲惨な現状を見れば、あえて論証の必要はないであろう。成功例は一つもない。
また、資本主義国、先進国において、近代経済学なるものが「国民経済を豊かにするために特別に役立った」という記憶も無い。むしろ、彼らが行う「経済予測」や「(経済)政策提言」などは、呪術師による神のお告げと同等のものである。当たるも八卦、当たらぬも八卦でその精度は地震予知さえはるかに下回る。
アダム・スミス以降の経済学は、ギリシャ・ローマの偉大なる繁栄が終わった後キリスト教会(カトリック教会およびその分派)によって専制支配された欧州の中世・暗黒時代に匹敵するほど悲惨な状況であったのである。
この中世・暗黒時代においては、ギリシャ・ローマにおける偉大な科学的・合理的精神は失われ、キリスト教というカルト宗教が暴力的(火あぶり拷問をはじめ)に人々を支配・洗脳した。
<ルネサンスによる解放>
しかし、幸運にも14世紀にイタリアから始まり16世紀ごろまで続いた「ルネサンス」が暗黒時代から抜け出す糸口を与えてくれたのである。
もっとも、スミスが生きた時代である18世紀にも宗教裁判はしばしば行われ、キリスト教会による残虐な拷問、八つ裂き・火あぶりの刑の犠牲者は現実に存在した。
その中で、スミスが合理的・科学的精神に基づく本書を執筆し出版したことはとても勇気のある行動である。我々はこの貴重な財産を正しく受け継ぐべきであったのに、前述のようにその内容がねじ曲がって伝わってしまった。
それはあたかも、ギリシャ・ローマ時代には「地動説」が当たり前のように語られていたのに、中世ヨーロッパにおいて教会から「天動説」を人々が押し付けられたようなものである。
アダム・スミス以降の経済学では、まさに「天動説」が如く、「(神に匹敵するような)偉い学者や政治家が経済を正しいあるべき姿にしてくれる」という信仰が広がったが、もちろんそのような考え方は間違いである。彼らが、一般の人類と異なるところなど何もない。 正しい「地動説」とは、「経済・社会などの複雑な事象(複雑系)をだれか特定の人間が恣意的にコントロールすることはできない」である。
幸いにも自然科学の最近の進展やインターネットをはじめとする通信・コミュ二ケーション手段の発達によって、経済や社会に関する「地動説」の正しさが実験などで検証できるようになった。
複雑系はもちろんだが、自己相似、相転移、臨界、ゆらぎ、遅れ、進化論、生物学、行動経済などの研究が「地動説」の証明に大いに役立ってきている。また、インターネットの発達によって、これまで目に見えなかった「人と人とのつながり」が通信データとして記録に残せるようになったことが、科学的な検証において極めて大きな役割を果たしているのだ。
多額な費用と膨大な労力を費やさなければならなかった社会実験が、低コストでごく簡単に行えるようになったのである。
<「写真」ではなく「動画」として理解すべき経済・社会>
アダム・スミスの著作としては「国富論」が有名だが、当時は「道徳感情論」の方がはるかに世の中に影響を与えた。
インターネットで「人と人とのつながり=ネットワーク」の詳細が明らかにされる前に、スミスは独自の観察眼によって、「人と人とのつながり=ネットワーク」すなわち社会や経済がどのような仕組みで動き機能するのかを、「道徳感情論」の中の【共感】という言葉で見事に説明している。
【共感】は人間の脳と脳をつなぐネットワークのきわめて巧妙な手段であり、このネットワークが自律的に指し示す方向に社会は動いていく。例えば雪や砂粒が積み重なっていき、ある「臨界点」を超えると雪崩を起こす。人間社会でも、脳のネットワークを通じた「共感」がある臨界点を超えると、急激な(社会)変動が起こる。
つまり、社会・経済の動きというのは、人間の脳のネットワークシステムである【共感】によって伝達され動かされるのである。特定の社会政策や、偉大なる特定の人物の手によってコントロールされるのではない。そのように見えても、それは単なる偶然の一致である。
サー・アイザック・ニュートン以来、アルバート・アインシュタインやニールス・ボーア(量子論)に至るまでの自然科学は、世の中の事象からその一部だけをまるで1枚の写真を切り取るようにして研究してきたが、それは動画のように絶え間なく動く現実世界の一瞬を、「SF映画のように時を止めて世の中をフリーズさせた姿」にしか過ぎない。
現実世界を理解するには「動画」は「動画」として解き明かす必要があるのだ。つまり「時の流れ」=「歴史」が今回のルネサンスにおいて重要なポイントとなる。複雑系や自己相似、さらには生物の誕生と成長、そして進化や遺伝子の世代交代など、現在の科学は「時の流れ」=「歴史」の問題にいよいよ踏み込もうとしており、それが【経済学ルネサンス】の追い風ともなっている。
本論文では、現在の【経済学ルネサンス】の状況を踏まえながら、ルネサンスの原点となるアダム・スミスの「国富論」と「道徳感情論」の二大著作の「真意」を論じる。
まず、「国富論:国の豊かさの本質と原因についての研究」について以下に論じる。
<人類とサルとを区別する高度な「交換」という行為>
人間とサルの違いは何か?世界のあらゆる分野の研究者の頭を悩ましてきた問題であり、筆者が子供の頃から興味を抱き、いまだに明確な解答を得ることができずにいるテーマでもある。
サルをはじめとする多くの動物は原始的な道具(例えば木の枝)を使用する。また、イルカはコミユ二ケーションに言語(音波)らしきものを使用することはよく知られている。さらに脳のサイズも、人間だけが特別大きいというわけでもない。
コイン(トークン)も、サルに教えれば、すぐに使い方を覚え、食べ物と交換したり「売・買春」(オスがメスに「食べ物に準じた」コインと交換に交尾を求め、メスがそれに応じる)も活発に行わる。売春が世界最古の職業であるとよく言われるが、本当かもしれない・・・
しかし、マット・リドレーがその著書「繁栄」で指摘するように、人間の行う交換は(換算の必要が無い)単純な等価交換だけでは無い。例えば、サル同士が「自分の背中をかいてもらったら相手の背中をかく」という交換をすることは珍しくないが、リンゴ一個を渡すかわりに背中を30分かいてもらうなどという高度な取引をするサルを見たことはない。このような価値の換算が必要な高度な交換は人間特有の行動であると言ってもよいだろう。複雑な価値の換算を行うのは極めて高度な知的活動であり、人間固有の行為なのである。
また、人間の行う交換には「交換の(実質的)先延ばし」というさらに高度な行為が含まれる。前述の「換算による交換」においても、現代においては「貨幣」がその仲介役として大きな役割を果たすが、「交換の先延ばし」においては、さらに貨幣が重要なものとして位置づけられる。
例えば、魚10匹と山菜一かごを交換したとしよう。どちらもすぐに消費しないと腐ってしまうから、交換はそれで終わりだ。ところが、塩と山菜を交換した場合、塩は保存可能である。そこで塩を受け取った人々は、それを自分で消費するのではなく、機会をうかがって、その塩をさらに別なものに交換することができる。これが「交換の先延ばし」ということである。
ちなみに、古代ローマにおいて(古代世界においてはほとんどの地域で)、塩が貴重なものであったため、ローマ兵の給与は塩で支払われていた。つまり塩が通貨の役割を果たしていたのである。ちなみに、サラリーマンの語源(大正時代から使われるようになったといわれる)はラテン語で塩を意味する「sal」だとされ、これは英語の「salt」 の語源である。
このような「人間とサルの違い」というテーマに関して、人類を「マネサピエンス」(カネサピエンス)と定義したい。ホモサピエンスとマネーやカネという言葉を合わせた、筆者の造語だが、生物学的定義はともかく、文化的に人類とサルとを区別する基準が貨幣(高度な交換)にあるのなら、それを駆使して繁栄した人類を「マネサピエンス」と呼ぶのは妥当だと考える。
<貨幣のパワーの源泉は【購入できる力】である>
国富論は、古代ローマからはるか時代が下った1776年に出版された。当時の通貨の中心は銀貨、金貨、それに銅貨である。銀貨が流通(価値尺度)の中心であったようだ。しかし、紙幣はもちろんのこと、銀行の当座貸し越し機能、金融機関などによる信用創造(融通手形など好ましく無いものも含めて・・・)など、現代の通貨・金融取引の基礎となるシステムはすべてそろっていた。
スミスは、それらの貨幣の根源的価値を基本的に「労働を購入できる力」と定義している(2次的には穀物などの生活必需品を購入できる力等)。
そして、現在注目されているのが(少なくともこれまでの基準では)価値の無い通貨すなわち仮想通貨である。
1971年に「ニクソンショック」が起こるまでは、ドル紙幣と金との交換はいつでも(一定の換算率で)行えた。つまり、少なくともドルについては、紙幣が単なる紙切れではなく、交換価値を持つ金に準じた商品であったわけである。
ニクソンショック以降、世界各国の政府は(実質的に)交換価値を持たない紙幣を印刷し続け、ドルを中心としたマネー(紙幣)は世界中にあふれている。この砂上の楼閣は半世紀ほど続いているが、今後どのような展開が待ち受けているのかわからない。
「交換価値」という呪縛を離れたマネーを獲得した人類がますます発展するのか、それとも「交換価値」の無い紙幣は単なる紙切れにすぎず、リーマンショック以上の大混乱を引き起こして、紙幣は紙くずになるのか、現時点では全く予想ができない。
さらに、紙幣には少なくとも「(暗黙の)国家や中央銀行の保証」がつくが、現在脚光を浴びているビットコインをはじめとする仮想通貨にはそれさえ無い。砂上の楼閣の上に、さらに砂上の楼閣の屋上屋を建てたようなものである。例えば、古代において貝殻や石貨が(仮想通貨として)流通した時期・場所があったが、現在貝殻や石貨では何も買えないことは改めて述べるまでもないだろう。
通貨(マネー)は国富論でも重要なテーマになっているが、あくまで「交換価値」を持つのが通貨の本質である。「金本位制」などと言うと、苔むした感じがするが、交換価値を持たない通貨が何らかの意味を持つとは思えない。別に金と交換する必要はないが、なんらかの「購買力」を保証することが、通貨(マネー)の本質であるはずである。
(第1回了、第2回に続く)
(文責:大原浩)
研究調査等紹介
高市一強。唯一の野党は資本市場。「ゲームの終わり」と仏教寺院
=第2次高市内閣の発足に際して考えること― 2026年2月18日、第2次高市内閣が発足しました。 2月8日の衆院選で自民党が単独316議席、戦後最多を記録。野党第一党の中道改革連合は公示前167議席から49議席へ、3 .....
明治維新という日本のプロテスタンティズム化 ── 日本の「文明受容パターン」の変質
伊勢神宮に学んだ日本的アニミズムの優雅さ 参照:<伊勢神宮に学ぶアニマ・フルネスの原点 | 神道とプロテスタンティズム、二つの世界観>https://j-kk.org/reports/%e4%bc%8a%e5%8 .....
伊勢神宮に学ぶアニマ・フルネスの原点 | 神道とプロテスタンティズム、二つの世界観
2026年1月24日(土)から25日(日)、私は伊勢神宮を参拝しました。 内宮・外宮への正式参拝に始まり、伊雑宮、瀧原宮・・・単なる観光ではなく、日本のアニミズムの核心に触れる、予期せぬ深い学びの時間でした。 前 .....
日本的「調整」とアニミズムの可能性 万物に神が宿る世界観が、分断を繋ぎ直す
「空気を読む」 日本人なら誰もが知るこの言葉は、外国語に翻訳することが困難です。英語で”Read the atmosphere”と訳しても、本質は伝わりません。 なぜでしょうか? 前回 .....